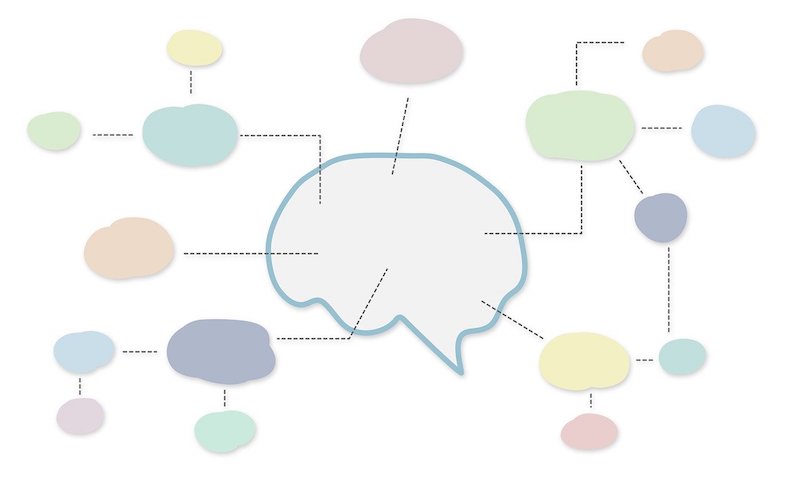どうも、基本情報技術者試験(FE)に合格したgordito(ゴルディート)です。
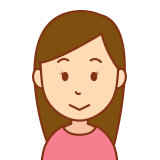
- 基本情報の午後対策として、各問題の『目標点数』と『時間配分』の目安を知りたい。
- 午後試験の『アルゴリズム』や『ソフトウェア開発』は時間が足りないけど、どうしたらいいの?
このような疑問や悩みを解決できる記事になっています。
なぜなら、戦略を立てて試験に合格した私が、目安となる『目標点数』と『時間配分』を紹介するからです。
記事を読み終えると、戦略を持って基本情報(FE)午後試験に臨むことができるようになります。
基本情報技術者試験(FE)の攻略法

午前試験対策 - 参考書の通読
午前試験の内容は次の通りです。
| 午前試験 | |
| 試験時間 | 150分 |
| 出題形式 | 多肢選択式 (四肢択一) |
| 解答数 (出題数) | 80問 (80問) |
| 合格基準点 | 60% |
前回の記事でおすすめした『キタミ式の参考書』や『合格教本』を1-2回、通読し、なんとなく理解できれば、午前試験は合格レベルに達します。
試験時間は150分ですが、ある程度勉強している受験生であれば、時間がなくて問題が解き終わらなかったということにはならないでしょう。
『午前試験』に関しては特別な対策や戦略がなくても、勉強量が足りていれば合格できるため、詳細な説明は省きます。
午後試験対策 - 各問題の『目標点数』と『時間配分』を設定
午後試験の内容は次の通りです。
| 午後試験 | |
| 試験時間 | 150分 |
| 出題形式 | 多肢選択式 |
| 解答数 (出題数) | 5問 (11問) |
| 合格基準点 | 60% |
出題数11問、解答数5問の内容は次の通りです。
| 分野 | 配点 | |
| 問1 | 情報セキュリティ | 20点 |
| 問2-5 | 次の中から3問出題 ハードウェア ソフトウェア データベース ネットワーク ソフトウェア設計 次の中から1問出題 プロジェクトマネジメント サービスマメジメント システム戦略 経営戦略・企業と法務 ※4問の中から2問選択 | 15点×2問 |
| 問6 | データ構造及びアルゴリズム | 25点 |
| 問7-11 | ソフトウェア開発 C Java Python アセンブラ言語 表計算 ※5問の中から1問選択 | 25点 |
令和元年(2019年)秋期試験までとは異なり、令和2年(2020年)春期試験からは次の3分野の配点が変更され、重要性が高まっています。
- 情報セキュリティ(12点→20点)
- データ構造及びアルゴリズム(20点→25点)
- ソフトウェア開発(20点→25点)
基本情報技術者試験(FE)の難問とされる『データ構造及びアルゴリズム』と『ソフトウェア開発』の重要性がより高まったわけです。
一方、文系受験者の得点源であるマネジメント系(プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント)、ストラテジ系(システム戦略、経営戦略・企業と法務)の重要性が低下しています。
また、『午前試験』とは異なり、『午後試験』は試験時間が足りないと感じる受験生が多い傾向にあります。
そのため、『午後試験』は戦略を立てて臨む必要があり、時間が足りない受験者(ほとんどの受験生)は戦略なくして合格できないと思った方が良いでしょう。
基本情報(FE)午後試験の『得点源』を把握
戦略を立てる前に『現状把握』が必要です。
まずは、午後試験の『得点源』と『得点源以外』を把握しましょう。
一般的な受験者であれば、基本情報(FE)午後試験の『得点源』は次の3問(以下、前半3問)になるでしょう。
- 問1の情報セキュリティ(1問20点)
- 問2-5の選択問題(2問30点)
→合計50点
そして、『得点源以外(=難問)』は次の2問(以下、後半2問)になると思います。
- 問6のデータ構造及びアルゴリズム(1問25点)
- 問7-11のソフトウェア開発(1問25点)
→合計50点
いきなり、このような区分けをされても納得できないことでしょう。
しかし、基本情報技術者試験(FE)の勉強を始めて『午後試験』の過去問を解き進めていくうちに、納得して頂けると思います。
まだ勉強を始めていない方は、『ふーん』という状態で大丈夫です。
基本情報(FE)午後試験の『目標点数』と『時間配分』
先ほどの『得点源』と『得点源以外』の区分けを踏まえると、次のような戦略を立てるのが現実的だと考えています。
- 前半3問で7-8割(35-40点)
- 後半2問で4-5割(20-25点)
そして、次のような時間配分が望ましいと考えています。
- 前半3問で1時間(+20分程度を許容)
- 後半2問で1時間30分(−20分程度を想定)
もちろん、『目標点数』も『時間配分』も個人差があるので、あくまでも1つの目安と考えてください。
また、『時間配分』に関して留意点が2つあります。
留意点1
前半3問の時間配分は1時間としましたが、考える時間を確保すれば点数が伸びるようであれば、10-20分オーバーしても問題ありません。
というのも、後半2問は2時間かけても2-3割の点数しか取れないような問題もあるからです。
実際、私は『ソフトウェア開発』の問題で『アセンブラ言語(CASL2)』を選択しましたが、30分程度で満点を取れる過去問があった一方で、1時間以上かけても2-3割の点数しか取れない過去問もありました。
どのような問題にも対応できる受験者でない限り、『かかった時間』と『取れる点数』は正比例の関係になりにくく、点数が安定しにくいです。
つまり、後半2問は費用対効果が悪いのです。
そのため、前半3問は点数を稼ぐために多少の時間オーバーは許容しましょう。
留意点2
後半2問で1時間30分と決めるのではなく、各問45分と決めて(半分半分にする)、その時間が経過したら次の問題に移りましょう。
私もやりがちでしたが、『あと少しだけ・・・』と考えて1つの問題に固執すると、もう1つの問題に十分な時間を割くができず、点数が伸びにくくなります。
深追いはせず、45分±10分程度で次の問題に移りましょう。
後半2問は問題を解き始めると、のめり込みやすいです。
繰り返しになりますが、過度に固執しないことが大事であるということを覚えておいてください。
選択問題の選択方法
基本情報(FE)午後試験は複数の選択問題があり、どの選択問題を選ぶべきか悩む受験者もいることでしょう。
そのため、どの問題を選択すべきか簡単に紹介します。
より詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

問2-5
| 分野 | 配点 | |
| 問2-5 | 次の中から3問出題 ハードウェア ソフトウェア データベース ネットワーク ソフトウェア設計 次の中から1問出題 プロジェクトマネジメント サービスマメジメント システム戦略 経営戦略・企業と法務 ※4問の中から2問選択 | 15点×2問 |
出題可能性から考えると、次の5分野の重要性が高いです。
- ハードウェア
- ソフトウェア
- データベース
- ネットワーク
- ソフトウェア設計
そのため、『時間のない人』や『効率的に合格したい人』であれば、この5分野だけ勉強すれば良いでしょう。
問7-11
| 分野 | 配点 | |
| 問7-11 | ソフトウェア開発 C Java Python アセンブラ言語 表計算 ※5問の中から1問選択 | 25点 |
既に勉強しているのであれば、『C』、『Java』や『Python』を選択するのが良いと思いますが、そうでない人は『アセンブラ言語』か『表計算』を選択するのが無難です。
下手に難しいプログラミング言語に挑戦しようとすると火傷します。
Excelが得意な人は『表計算』を選択するのが良いかもしれません。
基本情報(FE)の試験当日の様子

私が受験した時は、紙ベースの試験でしたが、現在は基本的にITパスポートのようなCBT(Computer Based Testing)方式での試験となっています。
そのため、ここから紹介する『想像以上に途中退出者が多いこと』と『受験者の年齢層のこと』はあまり参考にならないと思います。
一応、残しておきますが、目を通さなくて大丈夫です。
基本情報(FE)の途中退出者
私は試験当日、『午前試験』の時間を120分だと勘違いし、めちゃくちゃ焦りました。
というのも、前の席に座っている受験者が途中退出可能な時間(試験開始60分後)になったら、すぐに退出したので、時間の感覚がおかしくなったのです。
過去問を解いている時は、全部解き終わっても30分程度は時間が余っていたのに、なんで本番の試験ではこんなに時間が足りないのかと焦り、後半の問題はテキトーにマークしてしまいました。
ですが、120分経っても試験監督者が何も言わないじゃありませんか。
変に思って黒板を見ると、まだ30分も試験時間が残っていました・・・。
焦った私が馬鹿でした。
そこからはテキトーにマークした問題を含めて見直しを進め、事なきを得ました。
『午前試験』では途中退出者がそれなりにいます。
かなり早く途中退出する受験者もいると頭に入れておいてください。
そうすれば、試験当日にそのような場面に出くわしても焦らないと思います。
周りに惑わされた私の失敗談のようなものですが、参考にして頂けると嬉しいです。
基本情報(FE)の受験者層
受験地によって変わると思いますが、私が受験した会場は大学生が多そうでした。
あちらこちらで友達同士でわいわいがやがやしていました。
受験生の平均年齢は『20代半ば』なので、そのぐらいの年齢層が多いと思っていれば良いでしょう。
まとめ
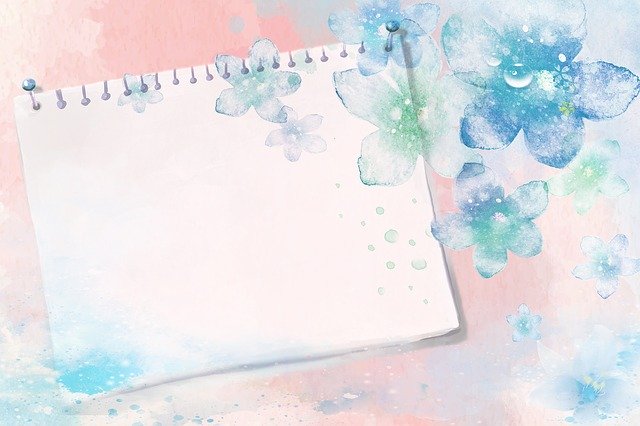
簡単にまとめます。
- 『午前試験』は勉強すれば合格レベルに達するが、『午後試験』は難問があり、また時間が足りないので『戦略』が必要。
- 『午後試験』は各問題に『目標点数』と『時間配分』を設定(前半3問は1時間で7-8割の点数、後半2問は1時間30分で4-5割の点数が1つの目安)。
いかがでしょうか。
基本情報(FE)午後試験に戦略を持って臨むことができるようになったのではないでしょうか。
この記事を読んで戦略を練った方が1人でも多く試験に合格することを願っています。
今回は、どの参考書を用いて、どのように勉強するべきかには触れていません。
おすすめの『参考書』と『勉強方法』に興味のある方には次の記事がおすすめです。

個人的には基本情報技術者試験(FE)の午後試験は難しいと感じると共に、将来的にプログラミングをやる予定のない受験者にとっては避けても良い試験だと感じています。
つまり、基本情報技術者試験(FE)を飛ばして、応用情報技術者試験(AP)に進むのも1つの選択だと考えています。
その理由を知りたい方は次の記事をご覧ください。